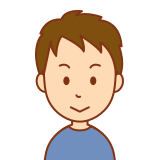
大容量のオートミールを買ったんだけど、どうやったら長期間保存できる?
冷蔵保存と冷凍保存はどっちがいいの?
常温で保存した場合の消費期限ってどれくらい?
こういった悩みを解決します。
本記事の内容
- オートミールの保存方法と保存期間
- 食べれないオートミールを見分ける方法
- おすすめのオートミール保存容器
本記事を書いている僕はオートミール歴4年です。オートミールはいつも2kg以上購入しています。1年前までは5kg購入していましたが、すべて腐らせずに食べきっています。
今回は、「オートミールの保存方法と保存期間」について解説していきます。
この記事では、オートミールの保存方法について、常温・冷蔵・冷凍それぞれの方法と期間を徹底解説します。
正しい保存で、いつでも新鮮なオートミールを楽しんでください!
それでは解説していきます。
オートミールとは?

オートミールは、イネ科の穀物である「オーツ麦(燕麦)」を加熱し、平たくフレーク状に加工したものです。
精白されていない全粒穀物であるため、胚芽や胚乳、外皮などが取り除かれずにそのまま付いており、栄養が豊富です。

玄米のような感じです。
1食あたり約105キロカロリーと低カロリーであることも特徴です。
オートミールの種類と特徴
オートミールには加工方法によっていくつかの種類があります。
- オートグローツ → オート麦からもみ殻だけ取り除いたもの
- スティールカットオーツ → オートグローツの一種
- ロールドオーツ → オートグローツを蒸してローラーで薄く伸ばしたもの
- クイックオーツ → ロールドオーツを細かく砕いたもの
- インスタントオーツ → クイックオーツに味を付けたもの
オートミールの栄養価と健康効果
オートミールは、食物繊維やビタミン、ミネラル類などの栄養素が豊富に含まれています。
特に食物繊維は、消化を助け、便秘解消にも効果があるとされています。また、ローカロリーであるため、ダイエット中の方にもおすすめです。

オートミールはその加工方法によって様々な種類があり、それぞれの食べ方を楽しめます。栄養価が高く、ローカロリーであるため、健康的な食生活を送りたい方にぴったりの食品です。
オートミールの保存方法と保存期間

オートミールの保存期間を解説していきます。
- 常温保存
- 冷蔵保存
- 冷凍保存
上記のような方法での保存期間ですね。
この3つの保存方法を知っていれば、いつもより長くオートミールを保存することが出来ますよ。
常温保存の場合
常温保存の場合、未開封なのか開封済みなのかによって、保存方法が変わります。
オートミールは湿気に弱いため、未開封の場合は乾燥した冷暗所での保存がおすすめです。

湿度の高い場所では、カビの発生や品質の劣化が進む可能性があるので、できるだけ避けましょう。
そうはいっても、梅雨や真夏のような季節になると、乾燥した冷暗所での保管が難しくなると思います。
そんな時は、冷蔵庫や冷凍庫での保存を検討するとよいでしょう。
袋を開封している場合は、プラスチックやガラスの密閉容器やジッパー式保存袋に入れ替えるのがおすすめです。
出来るだけ空気に触れないように、しっかりと封や蓋をして、涼しい場所で保存しましょう。

食品用乾燥剤を入れるとさらに安心です。開封後は、1ヶ月以内に食べ切ることを目安にしてください。
冷蔵保存の場合
冷蔵保存をする場合は、ジッパー式保存袋に入れ、小分けにして保存するのがおすすめです。
大容量のまま冷蔵庫に入れてしまうと、結露が発生してしまい、湿気やカビの原因になるので注意しましょう。
カビが発生すると食べれなくなるので、必ず小分けにしてから保存するようにしてください。
保存期間の目安は、2カ月程度です。
冷凍保存の場合
オートミールの袋を開封している場合、冷凍保存が最も効果的です。

冷凍保存の時のように、ジッパー式保存袋に入れ、小分けにして保存してください。
水でふやかして冷凍する場合には、食べ切れる量を小分けにし、ファスナー付保存袋に入れて空気を抜いて保存するか、密閉できる容器に入れて保存しましょう。
保存期間は2カ月程度です。
1食分ずつ保存するとき
1食分ずつジッパー式の食品保存袋に入れると、使いたい分だけ取り出せるので便利です。
それに、冷蔵庫から出し入れする回数を減らせるので、湿気を防ぐことが出来ます。
冷凍するときは、袋に入れた後、できるだけ空気を抜いてから密封するようにしてください。空気を抜くことで、冷凍時の乾燥を防ぎ、風味を保つことができます。

金属トレーに載せて冷凍すると、急速に冷凍できます。急速冷凍することで、氷の結晶が細かくなり、食感や風味が損なわれにくくなります。
食べられないオートミールを見分ける方法

オートミールを保存していると、消費期限が怪しいなんてことがあると思います。
そんな時は、次の方法で食べられるかどうかをチェックしてみてください。
- 見た目で見分ける
- 匂いで見分ける
- 味で見分ける
もったいない、まだ食べれる!ともう食べれないオートミールを食べてしまってお腹を壊す。
こういったことをなくすためにも、食べれるオートミールと食べられないオートミールの見分け方を身に着けておきましょう。
見た目で見分ける
まずは、見た目で食べれるオートミールかどうかを判断していきます。
消費期限が怪しいオートミールを開けて、カビが生えていないか、ネバネバしていないかをチェックしてください。

冷蔵庫に保存していても、保存容器内に結露ができてカビが発生することがあります。
一応チェックしてください。
カビ臭かったり、変色していたり、カビのようなものが生えていたりしたら食べずに廃棄しましょう。
ネバネバして糸をひいている場合も、腐っている可能性が高いので、すぐに廃棄してください。
匂いで見分ける
次は、オートミールの匂いを嗅いでみてください。
正常な匂いだと、オートミールは穀物特有の香ばしい匂いがします。袋を開けた時の匂いですね。
匂いがないなという場合もあると思いますが、これならまだ食べられます。大丈夫です。
問題は、すっぱいツンとした匂いや明らかな悪臭がする場合です。腐って傷んでいる可能性があるので、食べないようにしてください。
味で見分ける
見た目、匂いが大丈夫でも、味がダメな場合もあります。
腐っていないか心配なオートミールがある場合は、少量だけ味見をしてみてください。
正常なオートミールだと、穀物の香ばしさを感じるあっさりとした味を感じるはずです。
もし、酸味を感じることがあれば、そのオートミールは腐っている可能性があります。
舌を刺激するようなピリッとした苦みや辛味がしたら、傷んでいる可能性が高いため、食べるのをやめてください。
オートミールの保存時の注意点

オートミールを保存する場合、次の点に注意するようにしてください。
- 湿気を避ける
- 結露に注意する
オートミールは湿気にとても弱いため、保存時に湿気を避ける必要があります。
特に、冷蔵保存する際には結露に注意してください。結露ができることで、オートミールに湿気がこもり、カビができる可能性もあります。
基本的に湿気に気を付ければ長期間保存できます。
小分けにするといった工夫をして、美味しいオートミールを食べてください。
オートミールのおすすめの保存容器3選

今回は、オートミールの保存に最適な容器を3つ紹介します。
ぜひ参考にしてください。
カインズのワンプッシュ開閉容器
カインズの「ワンプッシュで開閉できる保存容器 1.0L」は、容量が1.0Lの保存容器で、価格は880円(税込)です。
この容器は、ワンプッシュで簡単に開閉ができるのが特徴で、楽にオートミールを保存することが出来ます。
また、材質や耐熱・耐冷温度も考慮されているので、オートミール以外の保存容器としても使用できます。
- 容器の上から簡単に押すだけで開閉ができる
- 湿気・臭気防止
- 熱湯消毒・食洗機対応
- 分解して洗いやすい
- 内容物の取り出しや入れ替えがスムーズに行える
無印良品のバルブ付き密閉保存容器
無印良品の「バルブ付き密閉保存容器 深型・中」は、容量が約幅12×奥行20×高さ8cmの保存容器で、価格は990円(税込)です。
この容器はエンジニアリングプラスチックを使用し、耐熱耐冷温度に優れています。それに、フタのバルブを上げることで、そのまま電子レンジでの加熱が可能です。
1食分の保存に利用すると、そのままホットオートミールやオーバーナイトオーツを作ることが出来るのでかなり便利です。
- 電子レンジでの加熱が簡単
- そのまま器として使える
- 中身が見えるので食べ忘れを防止
- 耐熱温度は140℃、耐冷温度は-20℃
- 軽くて割れにくい
ジップロックのフリーザーバッグ
ジップロック®フリーザーバッグは、旭化成ホームプロダクツが提供する冷凍保存専用のバッグです。
野菜や肉・魚の冷凍からレンジ解凍まで対応しているおなじみの、密封ジッパーです。
浸かっている人は良く知っていると思いますが、冷凍室の収納や整理整頓に適しています。
オートミールをすぐに食べれるふやかした状態で保存したい人におすすめです。
- 密封ジッパー
- 冷凍からレンジ解凍
- タブが色分けされていて分類しやすい
- 保存した内容や日付を書き込めるスペースがあり、管理が簡単
まとめ
オートミールを保存する場合は、湿気に気を付けるようにしましょう。
特に開封後は、湿気や虫の混入を防ぐため、密閉容器などに移し替えるのがおすすめです。
湿気の多い季節などは、冷蔵や冷凍を行って、オートミールの保存期間を延ばしましょう。
もし、消費期限が怪しいオートミールがある場合は、見た目、匂い、味で食べられるかどうかを判断することが出来ます。
ちょっとでもおかしいと思ったら、お腹を壊す前に廃棄してください。





コメント